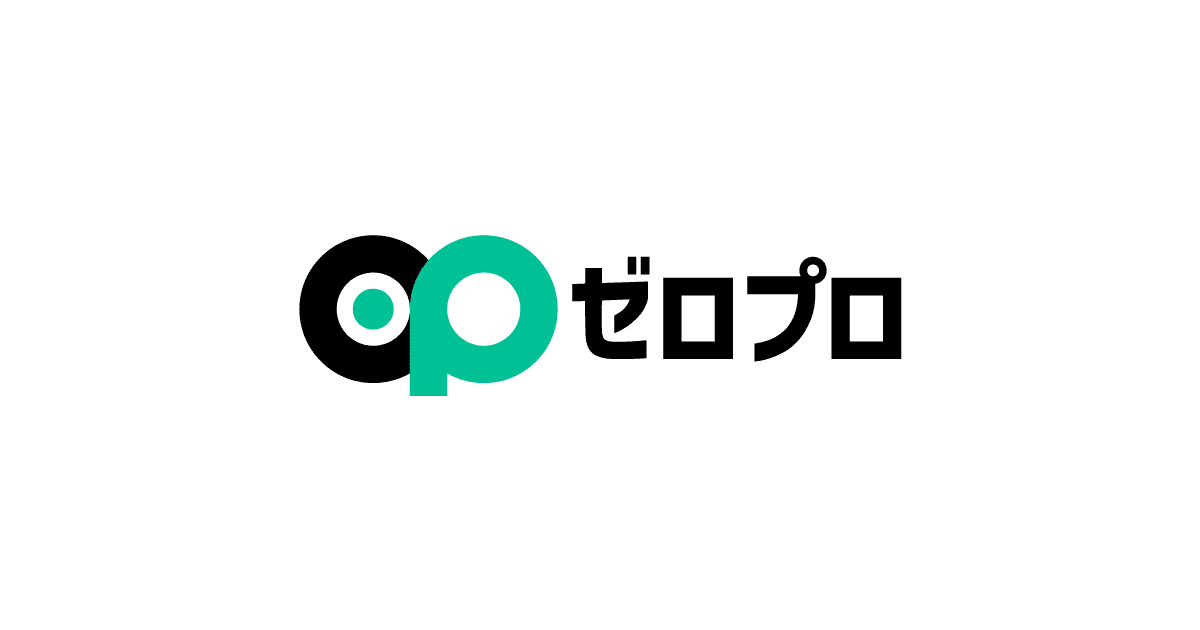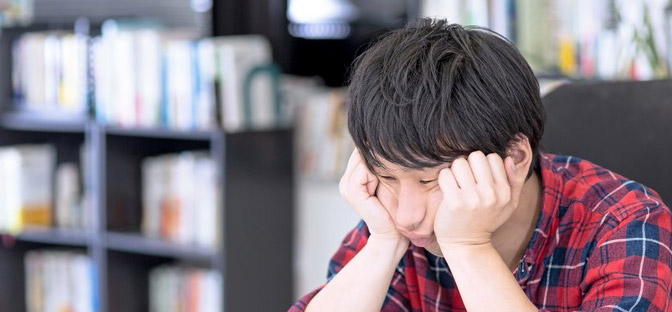プロパンガス料金の仕組み ~自由料金制と二部料金制~
更新日: 2022-10-07皆さんも当たり前のように毎日使っているガス。しかし、ガス料金がどのような料金体系かを普段から気にすることはありませんよね。都市ガスは定められた一定の基準に沿った料金ですが、プロパンガスの料金はプロパンガス会社が自由に決めることができるのです。ご存じない方も多い、プロパンガス料金の仕組みをご説明致します。
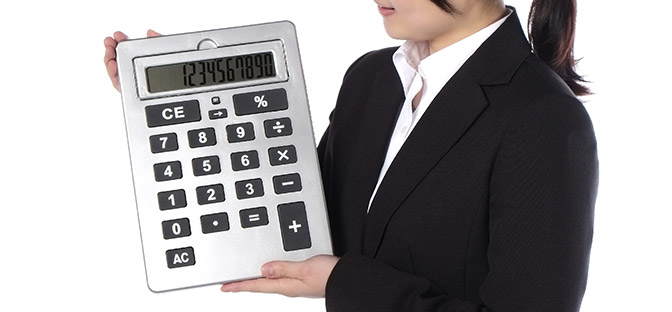
ガスは基本料金+従量料金の二部料金制
都市ガスかプロパンガスかに関わらず、ガス料金は二部料金制をとっています(使用量が多い場合や業務用でご利用の場合は、従量料金のみのケースもあります)。
二部料金制とは、基本料金と従量料金の二部体制で徴収する料金体系のことです。都市ガスとプロパンガスは同じ二部料金制ですが、ガス料金の決め方に大きな違いがあります。
都市ガスの料金は認可料金制となっています。行政が地域性や経済状況などを鑑みて、料金を認可する制度です。そのため、地域Aと地域Bでガス料金が異なることはあっても、地域Aの中では同じ料金設定となっており、利用者にも非常にわかりやすいですね。
※2015年7月現在は上記の通りですが、都市ガスも自由化されるようですので、いずれは料金にも違いが生まれサービス競争が起こる可能性が高いです
プロパンガスの料金は灯油やガソリンと同じ、自由料金制となっています。ガソリンスタンドによってガソリンの価格が異なるように、プロパンガス会社ごとにガス料金が異なっています。プロパンガス会社が自由に料金を設定できるため、同じ地域内でもガス料金が大きく異なります。そのため、より安いプロパンガス会社を選択することでかなりお得になるのです。
毎月かかる"基本料金"とは
ガスの使用量に関係なく、毎月のガス代に含まれてくるのが基本料金です。基本料金の金額はご家庭ごとに多少異なりますが、ガスを使わなくても必ずかかり、ガスのメーター1つごとに固定料金として毎月徴収されます。
基本料金はガスを供給するための設備費用や保守、保安、検針等の費用にあたります。
プロパンガスでは、基本料金もプロパンガス会社によって異なるため、基本料金が安いこともプロパンガス会社を選ぶ一つの目安となるでしょう。都市ガスでは、プランやガスの使用量によって基本料金が変動することがありますが、プロパンガスの基本料金はガスの使用量に関わらず一定であることがほとんどです。
使った分だけかかる"従量料金"とは
二部料金制に含まれるもう一つの料金、従量料金。こちらは毎月の基本料金とは別に、ガスの使用量に応じて決まる料金です。都市ガスもプロパンガスも1m3(立方メートル、立米と読みます)ごとの"従量単価"が設定されていますので、その月に使用した量×従量単価が従量料金となります。プロパンガスの場合、この従量単価もガス会社が自由に決めることができるので、従量単価の高いプロパンガス会社を選んでしまうと、毎月のガス代がかなり高額となってしまいます。逆に安いプロパンガス会社を選ぶことができれば、都市ガス並みの料金水準でプロパンガスを利用することも可能です。
ご存知の方も多いと思いますが、ガスの使用量は毎月のガスメーターの検針によって決定されます。また、プロパンガスの従量料金は、原油価格や国際運送費などを鑑みて決定されます。そのため、原油の輸入価格(CP=コントラクトプライス)が高騰するとプロパンガスも値上がりしてしまうこととなります。
都市ガスも使用量に応じて従量料金が決定します。専用料金が定められていることもあるかもしれませんが、基本的には地域毎に一律の料金設定です。しかしプロパンガスであれば、同じ地域でありながら、ガス料金を比較してガス会社を選択することができますから、都市ガスとは異なり自分でガス会社を選定する必要があります。
この記事を書いた人
無料相談・お問い合わせ
プロパンガス会社変更でアパート経営の利益最大化!
お困りごとなど、お気軽にご相談ください
弊社スタッフが丁寧にお伺いいたします