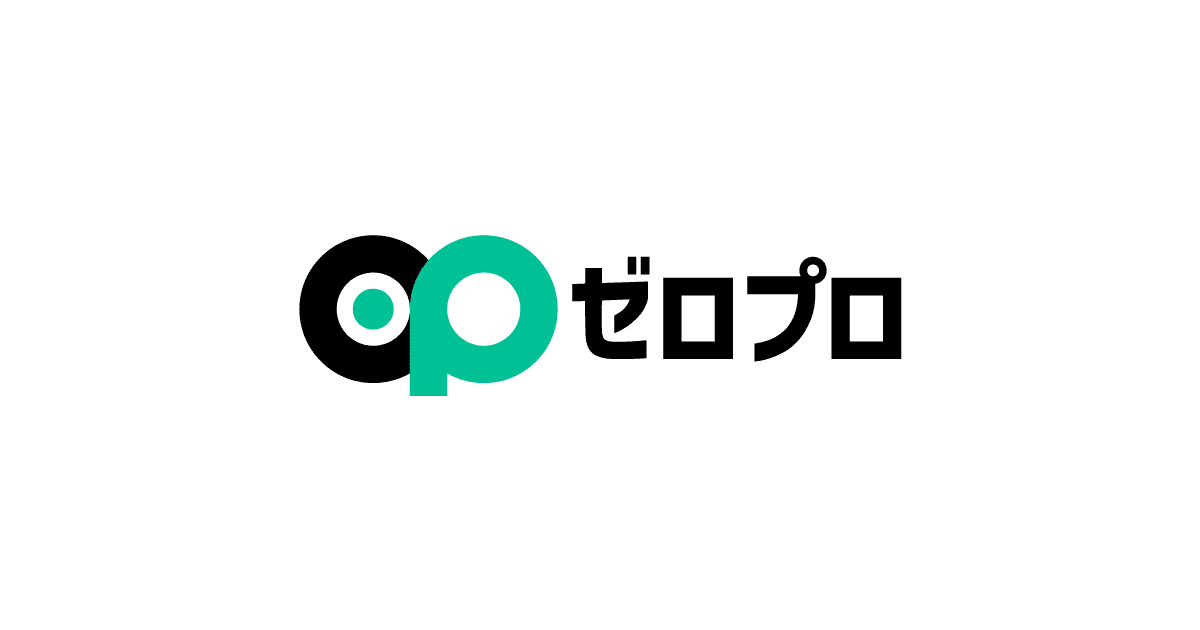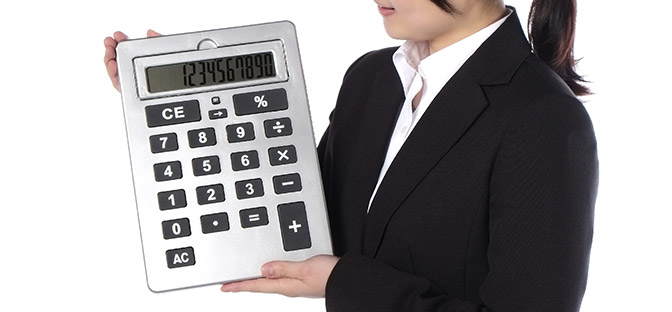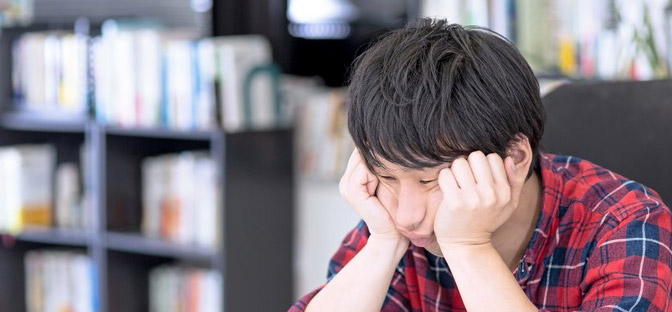絶対に失敗したくない!新築アパート経営の失敗例と対策
更新日: 2022-10-07アパート・マンションの賃貸経営をしていれば、誰もが「絶対に失敗したくない!」と思っているはずが、当然ながら経営がうまくいかずアパートを手放さざるを得なくなる人もいます。
どんな失敗例があるのか、初歩的な内容を一部ご紹介したいと思います。

節税対策はウソ?新築アパート経営での勘違い
失敗例の一つ目は「節税効果をちゃんと理解していなかった」というものでした。ただ土地を所有しているより、建物を建てた方が節税になると見聞きされた方は多いと思います。
減価償却費の控除や諸経費の控除によって確定申告時の所得額を抑えられる点も重要ですが、固定資産税等は特例条件を満たせば税額控除が受けられるのもポイントです。
実際に、所有する土地に賃貸住宅があった場合、固定資産税は通常の6分の1、都市計画税は3分の1になります(一戸あたりの土地面積が200平方メートル以下の場合)。2015年現在だと、新築の場合、要件を満たす部分の固定資産税減税を受けることができます。
そういった理由から、節税対策としてアパートを新築するオーナー様も多いようです。ただ、前述した新築の場合の減税については、3年または5年経過すると減税がなくなり、支払う税額は増えてしまいます。また、固定資産税には負担調整措置があるため、負担水準(前年度課税標準額/今年度評価額×住宅用地特例率(6分の1または3分の1))が100%未満の場合にも、税額が増えてしまいます。それを考慮せずに設備の過剰投資をしてしまうと、想定よりも支出が増えてしまい、収支が赤字に向かうこともありえます。
アパートを建てたからには、賃貸経営を行わなければなりません。賃貸経営に際しても入退居にともなうクリーニングなどの原状回復費用や、給湯器や水周りなどの定期的な修繕費用など経費がかさむため、状況によっては節税で生まれた黒字分を上回る支出を生んでしまいます。長期の節税効果も重要ですが、新築アパートの経営をお考えの場合は、実際に経営をされているオーナー様の話を聞いたり、上記した支出等も踏まえてしっかりと試算をするなど、慎重に検討する必要があります。不用意に「節税対策」の文字に踊らされないようにしましょう。
想定利回りだと黒字だから、成功は間違いない?
失敗例の二つ目は「周辺調査や賃貸経営の試算が甘かった」というものです。さすがに、満室時の利回りだけを見て問題ない!と信じきる人はあまりいないと思いますが、試算を行う際にはひょんなことが抜けてしまうことも。入居者の需要変化を読みきるのは至難ですから、完璧な試算を行うのは難しいですが、なるべく多くのリスクを想定する必要があります。
賃貸経営のシミュレーションで重要な入居率(または空室率)ですが、新築アパートは最初の入居者はスムーズに見つかることが多いようです。しかし、最初の入居者が退去した後、次の入居者を探す段階で苦労することがよくあると聞きます。周辺環境が変化して借り手の需要も変わってしまうことが要因になりやすいようで、「近所に新しいマンションができた」「近くにあったスーパーが閉店した」など、入居者の生活に関わる変化は如実に影響します。中には「近くにあった大学が移転し、入居者0になってしまった」という極端な例もあるようです。
設備状況が万全なのに入居者が決まらないようだと、今度は家賃を下げるなど直接的な対策を講じなければならず、家賃収入が減り資金繰りがうまくいかなくなる…と負の連鎖を招く可能性があります。そうならないためにも周辺状況を詳しく調査し、公示されている開発予定など将来的な状況をできる限り想定したシミュレーションを行うことで、なるべくリスクを抑えた運用をしていきたいところです。先達たちの体験談から学び、対策を考え、より安定した経営ができるように心がけたいですね。
この記事を書いた人
無料相談・お問い合わせ
プロパンガス会社変更でアパート経営の利益最大化!
お困りごとなど、お気軽にご相談ください
弊社スタッフが丁寧にお伺いいたします